最近、友人に勧められてジャック・ロンドン著「火を熾す」を読んだ。
その本を勧められたのは山を歩いている時で、ボクが火打ち石を使って白樺の樹皮を燃やすと、その様子を見ていた友人がふとその短編を思い出し、ボクに読むように勧めたのだ。で、その際にざっとした粗筋を聞き、「あれ? その物語、どこかで読んだぞ」と、記憶の山を掘り起こし、すぐに星野道夫さんの本だと思い当たった。
とりあえず図書館に行ってジャック・ロンドンの短編集「火を熾す」(その短編集のタイトルが「火を熾す」で、一番最初に収められている)を借りてきて読んだ。
マイナス50度という極寒のアラスカを旅する一人の男が、川で濡れた靴と靴下を乾かそうとして火を熾す。一度は勢いよく燃え上がる炎。しかし焚き火の上には木の枝があり、その枝には雪が積もっていた。焚き火の熱によって枝の上の雪は落ち、無残にも勢い良く燃え上がった炎を消してしまう。パニックになる男。が、アラスカの容赦のない寒さは、あっという間に男の手足の感覚を奪い、しまいには命までも奪ってしまう。
それだけの物語だが、大自然の持つ恐ろしさを骨の髄まで感じさせられる物語である。
で、やはりかつて読んだ星野さんのエッセイの中に、この物語に触れていると確信して、久しぶりに読み返してみると、「イニュニック」というエッセイ集にその短編が紹介されていた。
ご存知かと思うが、星野道夫さんは写真家としてアラスカの大自然を紹介し、そのエッセイでも素晴らしい文章を綴っている。だが残念なことに撮影中にヒグマに襲われ、43歳の若さで急逝された。
久しぶりにそのエッセイを読むと、ジャック・ロンドンの描くような大自然の怖さも描かれているが、その視線はどこまでも柔らかで優しく、読んでいて心の中に小さな焚き火を熾したような、ほんわかとした温かい気持ちに包まれる。
ちょっと寒さを感じ始めたこの季節に、とてもしっくりと来るエッセイ集である。





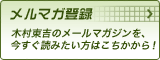





最近のコメント